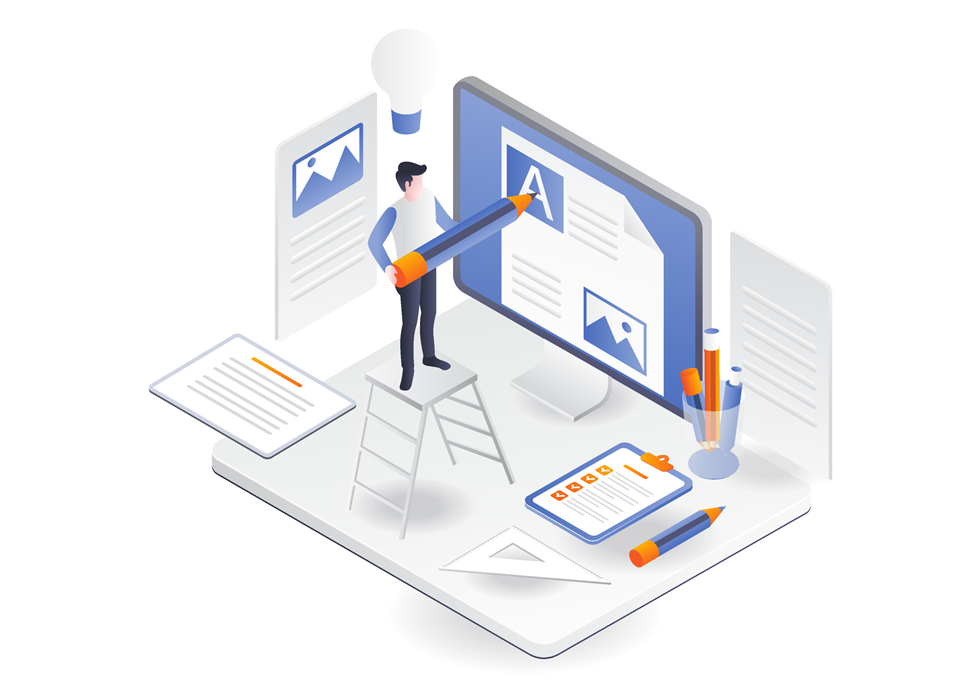こんな疑問にお答えします
本記事の内容
- なぜ文章を書くのが苦手と思ってしまうのか
- 文章力を向上させる13の方法
本記事の執筆者
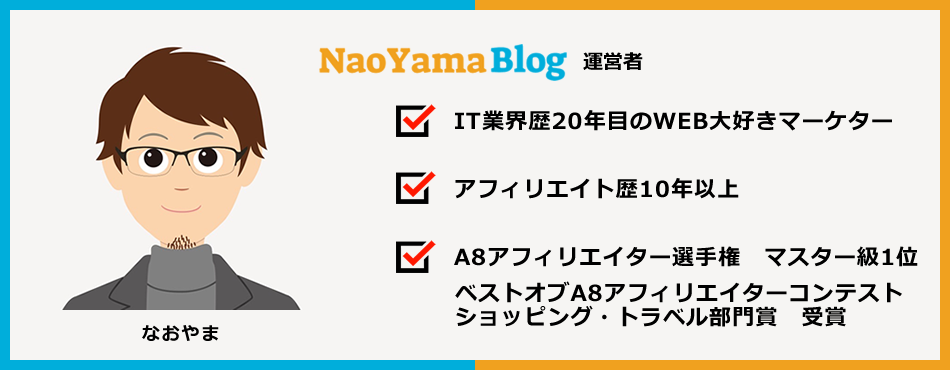
文系なのに国語が得意ではなかった僕。
成績は1もしくは2を行き来するほどの苦手っぷり。
感想文や小論文の作成は、いつも悩みました。
社会人になっても、この問題は解決しませんでした。
文章を書く業務があると、他人に頼んだり、デザインでごまかしたりして避けてきました。
そんな文章を書くのが苦手な僕でもブログを始めたことで、文章が書けないという問題を克服できたのです。
具体的な克服方法を、この記事を読んでいるあなたにだけ教えます。
こんな方々には特に読んで欲しい記事になっています。
- ブログを始めたいけど継続が心配な人
- 文章作成が苦手だと感じる人
- 文章力を上げるヒントを探している人
この記事を読み終えるころには、文章作成が苦手な理由から、挑戦してみようかと思えるようになるでしょう。
なぜ文章が書くのが苦手と思ってしまうのか

文章が苦手だと感じる人にはいろいろな背景があります。
たとえば、
- 学生時代に国語の成績が悪かった
- 長い文章を書くのが苦痛だった
- 文章を書くための知識やスキルが不足していた
- 文章の書き方に自信がなかった
- 語彙力がない
自慢ではありませんが、僕はこの5つ、全て当てはまります(笑)
小さいころは、マンガばかり読んでいて、本をほとんど読みませんでした。
たしかに、ドラえもんやキン肉マンやドラゴンボールのようなマンガはよく読んでた記憶はあるのですが、活字に触れる機会が少なかった学生でした。
もうその頃から、
- 文章を書いても内容が支離滅裂になるだけ
- 「これでいいのか?」と不安になる
- 自分には、他人と比べて語彙力がない
と思ってしまい、筆がなかなか走らなかったのです。
そんな僕でも、どうしてブログを書くのが好きになったのか?
文章力を向上させる方法を見つけたからです。
この方法を身につけると、誰でも書く力を高められます。
僕が改善できたのだから、この記事を読んでいるあなたも上達するはずです。
文章力を向上させる方法13選

文章を書くのが苦手だった僕が、書くことが好きになり、文章力を向上させるために実践した13の方法を紹介します。
中には、「それはダメだよ」という疑問を抱かれてしまうかもしれない方法も含まれています
しかし、それを使うことによって罰を受けるわけでもありません。
自分自身の文章力を向上させられるので、結果として問題ないのです。
特に注意してほしい方法もありますので、前もって知っておいてください。
以下が、文章力を向上させるための方法です。
- 書き始める前に、読者が誰かをはっきりさせる
- 記事の構成を考えてから文章を書く
- 文章の「型」を覚える
- 文章は一文一義
- 難しい言葉や比喩表現は使わない
- 表記の揺れや誤字脱字がないかしっかりチェックする
- 完璧を求めすぎない
- Googleドキュメントの利用
- ChatGPTを使う
- 憧れのブロガーの記事を写経、または繰り返し読む
- 苦手意識を無くすためには、何度も書く
- 添削企画に参加する
- 読書量を増やす
それぞれ解説していきます。
書き始める前に、読者が誰かをはっきりさせる
文章を書き始める前に、誰が読むかを明確にすることが重要です。
目的を持って書くと、言葉遣いや表現を適切に選べます。
たとえば、初心者に向けて書く場合は、難しい言葉や専門用語を使うのは避けるべきです。
そうしないと、読者は理解できず、興味を失います。
そして、文章を読んでくれた人たちをどんな状態にさせたいのかも、必ず決めなければいけません。
- 紹介した商品を買ってもらいたいのか
- 問い合わせをしてもらいたいのか
- 教えたことを実践してもらいたいのか
- ブログにある他の記事も読んでもらいたいのか
- 自分のブログをブックマークしてもらいたいのか
YouTubeの動画の中で、「チャンネル登録と高評価をお願いします」とYouTuberが言っているのをよく耳にするかと思います。
これと同じで、ブログも読者に何か行動を促すべきです。
これを念頭に置いて記事を書くと、文章の終わり方が変わり、読者にクリアなメッセージを伝えられます。
記事の構成を考えてから文章を書く
いきなり、文章を書いても、絶対に良い文章は生まれません。
文章を書くのが好きになった僕でさえも、未だに記事を書く前には以下の点を必ず考えます。
- どんな問題を解説する記事にするか
- どんな結論にするか
- 結論に至った理由をどう説明するか
- 読者の理解を深める例はあるか
- 記事を読んだ読者には、どうなってもらいたいか
-
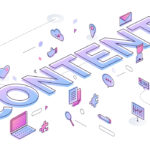
-
ブログの記事構成を作り方【記事の良し悪しは構成で決まる】
記事の構成を作ることによって、
- 記事に矛盾が出ないようにする
- 最初に考えた結論からずれないようにする
という問題が生じるリスクを減らせます。
このような問題が起きると、文章の修正を繰り返し、時間を無駄にすることになります。
だから、記事の構成はしっかりと考えましょう。
文章の「型」を覚える
「起承転結」や「PREP法」など、文章には「型」が存在します。
特にブログにはPREP法がおすすめ。
P:Point 結論
R:Reason 理由
E:Example 例
P:Point 結論
はじめに、【結論】を読者に伝えます。
これにより、読者は「なぜこの結論なのか」と疑問に思います。
次に、その【理由】を説明します。
こうすると、「理由は理解できた。もっと具体的な説明が欲しい」と読者は感じます。
そこで、分かりやすく解説するために、【例】を出してあげます。
読者の理解が増したところで、再度【結論】を伝えてあげることで、読者は「最初に言っていたことは、そういうことなのね」と納得してもらえるのです。
これはブログの世界だけに限った話ではありません。
クライアントに何か提案するようなビジネスシーンでも使うと効果があるので、試してみてください。

オリジナルでも問題ないのですが、多くのブロガーが文章を書く時に使っているPREP法などを使ったほうが、読者の理解が深まります。
慣れていない型だと
「どれが結論なの?」
「何が言いたいの?」
という混乱を起こしてしまう可能性があるので、できるだけ有名な「型」を使うことをおすすめします。
ちなみに、何か商品を売りたい時に役立つ型は、【セールスライティング】8つの型で商品が驚くほど売れる方法(例文とコツ付き)の記事で詳しく解説しています。
-

-
【セールスライティング】8つの型で商品が驚くほど売れる方法(例文とコツ付き)
ぜひチェックしてみてください。
文章は一文一義
一文一義とは、1つの文章に1つの情報だけを含めることです。
主張したいことが多いと、ついつい1つの文章の中にあれやこれやと詰め込みたくなります。
僕もよくやってしまう行為ではあるのですが、それでは、読者の頭の中には残りません。
「なんとなく面白かったけど、何が言いたいのか、よく分からなかった」ということになりかねません。
そうならないため、言いたいことだけを簡潔に伝えることが大切です。
文章を書き終えた後に、文章の校閲や校正をするかと思います。
》文章の質を磨く校正ツールの紹介【校正の基礎も学びましょう】
-

-
文章の質を磨く校正ツールの紹介【校正の基礎も学びましょう】
その時に、余計な情報や言葉は、できるだけ削ぎ落としましょう。
削ぎ落しすぎて、意味が変わってしまうことがあるので、加減の調整には注意が必要です。
難しい言葉や比喩表現は使わない
難しい言葉や比喩表現を使うのは、読者からすると混乱を生むだけ。
文章を書いていると、
- カッコいい言い回し
- 難しい漢字(四字熟語)を使う
- 分かりにくい比喩表現を使ってしまう
- あまり知られていないことわざを用いる
など、自分は言葉をよく知っていることをアピールする書き手がいます。
それは、読者を混乱させがちです。
僕も本を読んでいて、難しい言葉や表現を使う本に出くわしてしまうと、読むのに疲れてしまい、そっと本を閉じてしまいます。
ブログにおいても同じことが言えます。
誰もが理解できるシンプルな言葉を選ぶように心がけましょう。
表記の揺れや誤字脱字がないかしっかりチェックする
表記の揺れや誤字脱字は、一瞬で文章の信頼性が損なわれます。
せっかく、分かりやすい文章を書けたにもかかわらず、基本的なミスで全てが無駄になります。
たった1つの凡ミスで、「この内容は信頼できないかもしれない」と誤解されることもあります。
ですから、表記の揺れや誤字脱字がないか、チェックは必ずしましょう。
完璧を求めすぎない
最初から完璧を目指す必要はありません。
100%の完成度でないと、世の中には出せない、もしくは出してはいけないと思っているブロガーがいます。
ブログはいつでも更新や修正ができます。
完成度60%ぐらいでも、記事を公開しても大丈夫です。
だからといって、間違った情報を流していいわけではありません。
肉付けとなる情報は後から加えても問題ありません。
記事の完成度を高める工程の1つに、リライト作業があります。
-

-
ブログの効果的なリライトのやり方講座【ブクマ推奨】
リライト作業には、
- 新しい情報の追加
- 過去の正しい情報が現在では間違っている場合の修正
といった作業があります。
古い情報をそのままにしておくと、読者からの信頼を失う可能性もあります。
また、SEOでの上位表示も難しくなります。
》【完全保存版】SEO対策は何をすればいい?2024年最新SEOガイド
-

-
【完全保存版】SEO対策は何をすればいい?2024年最新SEOガイド
定期的にリライト作業が必要になるので、そこで情報を増やしていけば、徐々に完璧な記事に仕上げていきます。
完璧を追求しすぎて、新しい記事の発信が減ってしまうと、読者の期待を裏切ることになりかねません。
まずは60%の完成度をゴールに設定し、文章を書きましょう。
頻繁に新しい記事を書いていったほうがいいです。
そうすることで、書くことの楽しさを感じられるようになるでしょう。
楽しくなれば、文章力の向上にも良い影響が出るようになります。
Googleドキュメントの利用
僕は記事の原稿を書く時、WordPressに直接書き込むことはしません。
Googleドキュメントを使って、原稿を書きます。
Googleドキュメントの中にある文法チェック機能を使うことで、表記の揺れや誤字脱字のミスを減らせるからです。
瞬時に「あなたが書いた文章はおかしいですよ。正しくはこれではありませんか?」と指摘してくれます。
文法チェック機能を使うと、文章を書く際に自然に気をつけるようになります。
これが文章力を向上させるカギとなるのです。
ツールを使えば、文章がキレイに書けるようになりますし、自分のスキルアップにもなるので、積極的に利用しましょう。
ただし、1つ注意しなければいけないことがあります。
全ての文章の生成までも、ツールに任せようとしないこと
2024年3月5日にGoogleの検索アルゴリズムが変わる、コアアップデートが実施されました。
Today we announced the March 2024 core update & new spam policies that, in combination, are designed to show less content made to attract clicks and more content that people find useful. Learn more: https://t.co/wQVZ8mExRB
— Google Search Central (@googlesearchc) March 5, 2024
2024年3月のアップデートの中で、検索順位を操作することを主な目的としたユーザの役には立たないページ(スケールコンテンツ)を問題視しています。
特定はしていませんが、おそらくGoogleは、AIが作成した記事について指摘していると思われます。
AIライティングツールの普及で、AIに記事を作ることを任せている人たちが増えています。
-

-
おすすめのAIライティングツール12選【使わなきゃ損!】
AIライティングツールが作り出す記事は、基本ネット上にある情報を加工して、記事として生成しているのです。
そのため、独自コンテンツと呼ばれる、書き手が経験したことや、独自で集めたデータ(例:アンケートデータ)といったコンテンツが含まれていません。
AIが作った情報ばかりが、Googleの検索結果の上位を独占しても、「同じ情報ばかり」とユーザーは思ってしまい、Googleを利用する頻度が下がってしまいます。
そうなると、Googleを運営しているアルファベット社の約8割は広告収益で稼いでいますので、その売上が減少してしまいます。
このような問題が起きてしまわないためにも、Googleはスケールコンテンツは排除し、Googleの検索の質を上げていくと考えられるので、AIに頼り過ぎないコンテンツ(独自コンテンツ)を作り続けるべきなのです。
AIに頼りすぎると、将来的に検索結果で不利になる恐れがあります。
今は上位表示できていても、近い将来、再び来るであろうコアアップデートの時に順位を落とされてしまいます。
このような順位が落ちる体験を、この記事を読んでいるあなたに経験してもらいたくないので、長期的にブログ運営していきたいのであれば、今から依存を控えることが大切です。
ChatGPTを使う

ゼロからChatGPTに文章作成を任せたら、あなたの文章力の向上になりませんし、Googleからも低評価をされてしまいます。
ChatGPTは、文章の校正や校閲専用に使うべきです。
自分で行う校正や校閲が文章力を高めることは確かです。
だが、ChatGPTを使えば、より良い文章を書けます。
僕も最初は、ChatGPTなんかに任せられないと思ってた人間の一人です。
しかし、試しに文章の校正をさせたところ、自分の持っている知識だけでは書けないであろう文章に直してくれて、逆に勉強になったのです。
ですので、今では
- 自分でまず文章を書く
- ChatGPTに校正と校閲させる
- どのように文章が変わったのか比較する
- 次の自分で書く文章に活かす
こういう新しい循環が僕の中でできたのです。

まずは無料版のChatGPT3.5でも問題ありません。
ただ、何回も使っていくと、
- もう少し自然な文章にして欲しい
- いつも同じような文章ばかり
というように、もっとこうして欲しいという要望が出てくると思います。
そうしたら、有料版のChatGPT4を検討してみてください。
ただし、(有料版、無料版関係なく)ChatGPTが生成した文章が100%よくできているかと言いますと、そうでもありません。
自分が作った文章を、ChatGPTが誤って解釈し、全然意味が変わった文章に修正されることがあります。
生成された文章の内容が正しいかどうかのチェックは必ず行ってください。
憧れのブロガーの記事を写経、または繰り返し読む
憧れのブロガーから直接学べる機会はなかなかありません。
そのチャンスがあったとしても、高額な料金が必要になることが多いのです。
しかし、優れた技術を持つ人から学ぶことは、大きな成果につながります。
ゴルフで言えば、プロから指導を受けた方が、自己流よりも技術が早く正しく上達します。
これはブログの世界でも同じことが言えます。
しかし、高額な費用をそう簡単に払えないのが現実です。
そういう時には、憧れのブロガーがどのように記事を書いているかを徹底的に分析すると良いでしょう。
- どうしてこの人の文章はうまいのか?
- 文章に何か規則性があるのではないか?
という視点で記事を熟読することで、上手く書ける理由が見つかります。
なかなか見つけられない場合には、写経がおすすめ。
記事の写経、言い換えれば、記事をマネすることです。
そうすると、記事の書き方の癖(=マネすべき癖)が見えてきます。
見えてきたら、あなたの書き方にも取り入れていくのです。
マネて、自分なりにカスタマイズすることで、あなたオリジナルとなるのです。
文章力を向上させる近道なので、ぜひ試してみてください。
苦手意識を無くすためには、何度も書く
継続して文章を書くことで文章力は上がります。
初めは、短い文章でも構いません。
徐々に量を増やす方法が効果的です。
ブログに多くの記事を投稿することで、僕は苦手意識を失いました。
また、書いたものを他人に読んでもらい、フィードバックをもらうことは、技術の向上に役立ちます。
それが次の章の「添削企画に参加する」で説明します。
添削企画に参加する
添削企画への参加は気付きが得られる絶好の機会です。
/
🎆感謝企画第3弾🎆
\感謝企画も最終日となりました❣
最終日はブログ無料添削企画🌸
参加希望の方はリプ下さい✨ pic.twitter.com/wTrn3s9yFA
— エリコ🌸星読み&心理学で子育てを仕事に (@erimamachan7) June 8, 2021
\ブログ記事添削企画/
【限定先着5名様】
✅アクセス全然集まらない
✅稼げなくて挫折しそう・・・😭
なんとかしたいあなたのブログ、1記事無料で添削します!
添削後、500字程度の感想を書いてくれる方
先着5名での募集です。対象者は画像をご確認ください! 応募はリプもしくはDMまで😊✨ pic.twitter.com/F2FEO9BbVu
— せいせん@ブロガー (@seisen_log) November 25, 2020
/
ブログ添削企画🎁します!
\✅1/31までに公式LINEに登録
✅僕をフォローした方限定で、ブログを1記事無料で添削させていただきます!
登録後、「添削希望」とメッセージをお願いします!
公式LINEはこちら
👇https://t.co/ak9FkVeIWe#おは戦40112js #ブログ #ブログ初心者と繋がりたい
— とき@SNS×ブログ×マーケ (@toqiblog) January 11, 2022
無料で添削してくれる企画には、積極的に参加しましょう。
読者から直接感想をもらうのは難しいものです。
だからこそ、添削企画では忖度なしに指摘がもらえ、新たな気づきを得られます。
もちろん、「そんなの知ってるよ」「余計なお世話だよ」と感じる指摘もあります。
それでも、そう思う人もいるのかという気付きになるので、指摘を真摯に受け止めましょう。
受けた指摘を次の記事に生かせば、文章力が上がります。
読書量を増やす
なんだかんだ言って、読書量を増やすことは大事。
読書量を増やすことで以下の効果を得られます。
語彙力・表現力の向上
様々な文章に触れることで、語彙力や表現力が自然に向上します。
文章構成の理解
良い文章はどのように構成されているのかを学べます。
読解力の向上
文章を正確に理解する力が養われます。
読書が苦手な人は、興味のあるジャンルの本から読み始めましょう。
冒頭でも書きましたが、僕は赤川次郎の三毛猫ホームズシリーズや、星新一のショートショートを読んで、本の魅力に気づきました。
また、読むことが苦手な人には、ページ数が少ない本を選ぶことをおすすめします。
一冊を最後まで読み終える経験は、大変価値があります。
苦手な人ほど、「この本は、あと何ページだ?」みたいな意味のない行動をしがちです。
まずは短い本で読書の楽しさを見つけてみてください。
まとめ:【文章を書くのが苦手な人は必読】文章力を向上させる方法13選
本記事を簡単にまとめると…
本記事のまとめ
文章力を向上させる方法13選
- 書き始める前に、読者が誰かをはっきりさせる
- 記事の構成を考えてから文章を書く
- 文章の「型」を覚える
- 文章は一文一義
- 難しい言葉や比喩表現は使わない
- 表記の揺れや誤字脱字がないかしっかりチェックする
- 完璧を求めすぎない
- Googleドキュメントの利用
- ChatGPTを使う
- 憧れのブロガーの記事を写経、または繰り返し読む
- 苦手意識を無くすためには、何度も書く
- 添削企画に参加する
- 読書量を増やす
文章力を向上させるために、これまでに様々な方法を試してみました。
今回ご紹介した13の方法が、最も文章力を向上させてくれました。
この13個の中から、1つでもいいので試してみてください。
これがきっかけでブログ運営が楽しくなるかもしれません。
新しい記事を次々に書きたくなる自分がいるかもしれません。
「しょうがないな。そこまで言うなら」という気持ちで全然OKですので、チャレンジしてみてください。